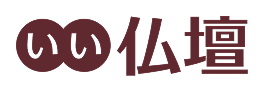飯山仏壇の起源とは?長野で塗仏壇が発展した理由

飯山仏壇は、長野県飯山市で生産される仏壇です。 飯山仏壇に使われている伝統的な技術・技法や起源について紹介します。
飯山仏壇の歴史
飯山仏壇の起源は1689年(元禄2年)。甲府から来た寺瀬重高という人物が素地仏壇を作ったことが始まりとされています。
塗仏壇の隆盛はそれからずっと後のことです。越後潟町から来た鞘師屋佐七が発案者であると言われています。飯山仏壇が発展した要因として、以下のものが挙げられます。
- 仏教信仰の篤い場所であったこと
- 城下町や寺社の政策
- 仏壇原材料(木材など)が地元にあったこと
- 漆塗りに最適な気象条件(清澄な空気、適度な湿気、豪雪)
- 立地条件
飯山仏壇の概要

飯山仏壇は、部品作りから組み立てまでの製造工程の全てが地域内で一貫しておこなわれています。主に製造されるのは、浄土真宗東本願寺派の仏壇です。
「伝統的工芸品」基準をクリア
飯山仏壇は1975年(昭和50年)9月4日、経済産業大臣により「伝統的工芸品」の指定を受けました。
伝統的工芸品とは優れた日本の伝統産業を後世へ継承するための基準。経済産業大臣が指定した条件を満たし、産地検査に合格した製品には伝統マーク入りの伝統証紙が貼られます。
飯山仏壇に定められた基準
- 木地の構造は「本組み」による組立式にする。
- なげしは弓形にする。
- 宮殿(くうでん)造りは「肘木組物」にする。
- 塗装は精製漆を手塗りする。
- 蒔絵および「艶出押し」による金箔押しをする。
- 木地は、松、杉、朴、または同等の材質を有する用材を使用する。
- 金具は、銅、銅合金、または同等の材質の金属製のものを使用する。
- 天然漆を使用する。
資料・画像提供:飯山仏壇事業協同組合