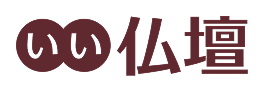仏壇・仏具・お墓の相続について
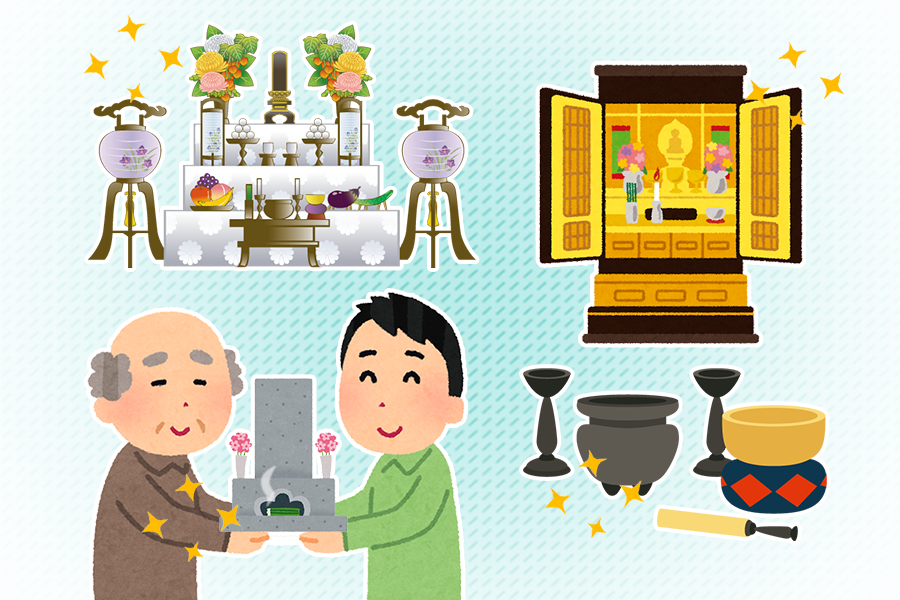
誰が相続するのか、はっきりと決めていない家庭も多いでしょう。
仏壇・仏具・お墓は先祖を祀るという性質から、法律上も、他の相続財産とは異なる扱いをされています。
いざ仏壇・仏具・お墓を相続する際に、揉めたり損をしてしまったりしないように、法律上の扱いを見ていきましょう。
祭祀財産ってどんなもの?
祭祀財産は誰が承継するの?
お墓や仏壇を分けて相続してしまうと、後々、先祖の供養などをする際に不便だからです。
祭祀財産を承継した者は、普段から仏壇やお墓の手入れをしなければなりません。
法事などを取り仕切るのも祭祀承継者の役目です。
遺言書での承継者の指定
一般の財産の場合には、遺言がなければ法定相続人が相続しますが、祭祀財産の継承者は必ずしも法定相続人に決まるとは限りません。
ただ、実際には長男が祭祀継承者になることが多いようです。長男が遠方の地域に住んでいて次男が墓地から近いところに住んでいるような場合には、他の兄弟が祭祀財産を承継することもあります。
また、故人が遺言書で指定さえすれば、結婚して苗字が変わった娘でも祭祀継承者になれます。
仏壇やお墓の相続とは?
一方、お墓を相続する際には、名義変更を行わなければなりません。
お墓の名義変更の手続きは霊園の管理者に対して行います。公的な手続きではないため、霊園によって手続きの方法がやや異なりますが、戸籍謄本の提出を求められることが多いです。
戸籍謄本は、お墓の前の管理者と、相続人との関係や亡くなった事実を確認するのに使用します。名義変更の手続きが完了すると、使用許可証を書き換えてもらえます。
名義変更をしないままにしておくと、無縁仏として扱われてしまう場合があるため注意が必要です。
事情によって仏壇を引き継げない場合は、仏壇を処分する必要があります。
仏壇処分は、自治体などにゴミとして処分してもらうこともできます。
しかし、故人の魂が宿った仏壇をゴミ処分するのは気が引ける方も多いと思います。
基本的には、魂抜きや閉眼供養などをして処分するのをおすすめします。菩提寺や近隣のお寺などに相談してみましょう。
お仏壇の処分は、専門業者や仏具店などが引き受けておりますので、ご供養が終わったあとは仏壇処分をしている業者に相談するのも良いでしょう。
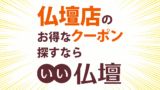
仏壇やお墓には相続税がかからない?
決して安いものではありません。
仏壇やお墓を相続したら、相続税を気にする人もいるでしょう。仏壇やお墓は、通常の財産と異なり相続税の対象外という扱いになります。
相続税がかからない財産とは?
経済的価値のある財産のほとんどは相続財産として扱われます。
しかし、仏壇やお墓などの祭祀財産は相続財産ではないため、相続税もかかりません。
祭祀財産を生前に購入すれば節税対策が期待できる
しかし、生前にお墓を購入しておけば、自分が亡くなったときの相続財産が、お墓の購入費用分だけ減るでしょう。
相続財産が減れば、相続税の金額も減り節税になります。資産の多い家庭では相続税の負担が大きいため、なるべく節税できるように、お墓は生前に購入しておくのが賢明です。
相続財産がぎりぎり基礎控除を超えてしまうくらいの財産なら、お墓を購入して、相続財産が基礎控除内に収まることもあります。
祭祀財産を購入するときの注意点
しかし、ローンで購入し、完済前に亡くなった場合には要注意です。
通常の債務と異なり、祭祀財産購入のために組んだローンの残債は、プラスの財産から差し引けません。
未返済の分が多いと、節税効果も弱まってしまいます。
また、高価な仏具を大量に買うなどした場合には、税務署から課税逃れと判断されてしまう場合があります。
また、仏具は供養で使用するのに必要な分しか祭祀財産として認められません。
まとめ
一旦祭祀承継者になった人は、亡くなるまでお墓や仏壇の管理を続けます。
本人の希望や住んでいる場所などを考慮して、小まめにお墓を管理できる人を選びましょう。なるべく元気なうちに決めておいて本人に伝えておくのが望ましいです。