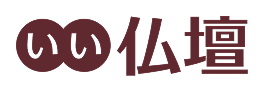節分と仏教について

節分の意味と歴史
旧暦(太陰太陽暦)では、立春は現在のお正月、節分は大晦日に当たりますが、明治5年に、翌年から旧暦を取りやめ、新暦(太陽暦)が採用されることが決まりました。それ以降、立春は現在の2月4日頃を指し、その前日の2月3日頃を「節分」というようになりました。
節分の行事の由来
中国では周の時代から、1年の終わりの大晦日に、疫病を引き起こしたり人を苦しめたりする疫鬼を追い払う「大儺(たいな)」という儀式を行って新年を迎えたとされます。時代によって方法は異なり、漢の時代には、呪師が疫鬼を追い出す役割を担い、手には矛と盾、顔には黄金の四つ目の面、熊の皮をかぶり、黒い衣を身につけていたようです。この儀式では「豆まき」も行われていたとされています。中国において、豆は生命力が強く、疫鬼を払うことができるものと信じられていました。
日本では「大儺」が「追儺」に
この儀式では、鬼を払う役目の役人が矛と盾を持ち、黄金の四つ目の面をつけます。貴族や官吏たちがそれにしたがい、「鬼やらい、鬼やらい」といって疫鬼を追い払いながら都の外まで練り歩いたそうです。この儀式は鬼を追いかけることから「大儺」は「追儺」と呼ばれるようになりました。
この宮中での追儺の儀式は、平安時代後期から戦などの影響で次第にすたれていきました。
節分と仏教行事
仏教では悪鬼や悪魔は心の中の煩悩を意味し、煩悩が災厄をもたらすと考えられていることから、煩悩すなわち悪鬼を追い払い、すがすがしい気持ちで新年を迎えるための行事として、定着していったといわれています。
一方、「豆まき」は同じ年代である平安時代後期に公家や貴族の間で行われ、室町時代に豆をまいて邪鬼を追い払う行事として広まったと考えられています。
そして、庶民が「豆まき」を行うようになったのは江戸時代といわれています。江戸時代には仏教が広く庶民の間に普及しましたが、それとともに寺院の節分会において、「豆まき」の行事が定着していったようです。
「豆まき」の意味・作法
そして、豆をまくタイミングは節分の日の夜が良いとされていますが、これは鬼が活動するのが夜だと考えられているからです。他には、厄除けに年齢プラス1個の豆を食べると良いとする風習などもあります。
まとめ
仏教行事について以外にも、仏壇のことでご相談したい方、見積もりが欲しい方は、お気軽に「相談フォーム」よりお問い合わせください。