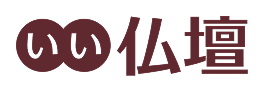位牌(いはい)の選び方

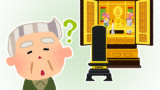
故人の戒名(法名・法号)を書いて仏壇に納める木の札のことで、遺された人たちが位牌を通して故人をしのびます。
ふと、故人に会いたくなったとき、そっと抱きしめてぬくもりを感じられるもの、位牌には魂と心を「つなげる」役割があります。
*早急でご準備が必要な方は「8.位牌を購入する仏壇店の選び方」をご参照ください。
位牌は必要なもの?
位牌がある:
供養の対象ができる。故人を身近に感じられる。また、引っ越しなど家を離れるときでも持ち運べるというメリットもあります。
位牌をお持ちの年配の方から、「お位牌は何年経っても、見れば両親を思い出す、怖い父だったとか優しい母だったとか、自分が童心に返る気持ちになれていいものですよ」という声をお寄せいただくこともあります。
一方、位牌を見ると悲しい気持ちが思い出されるという場合もあります。
位牌がない:
位牌に固執せず、遺影や遺品など故人の遺したものに思いを巡らせる。
一方、法要のときに不便を感じる。何か不幸が起きたときに位牌がないからかも、と不安になる方もいるようです。
位牌はいつまでに作るの?
購入した位牌は、魂入れをしてはじめて供養の対象になります。
位牌は四十九日法要までに用意
本来の「位牌」と呼ばれるものは、四十九日後にまつられるもので「本位牌」といいます。
四十九日までは「白木の位牌」という仮の位牌をまつります。
お葬式の後、本位牌は四十九日の法要までに準備します。法要の際にご住職に魂入れ(たましいいれ)をしていただき、白木の位牌から本位牌へと入れ替えます。
位牌を作らない宗派もある?
ですが、浄土真宗を信仰しているけれども位牌で供養をしたい、と思う方もいらっしゃるかもしれません。このような時にはお寺に相談してみましょう。それぞれのお寺や住職の考え方によっては位牌を作ることができたというケースもあります。また、専門家の視点から、よいアドバイスをいただけることもあるでしょう。
*宗旨・宗派、地域性などによっても異なります。詳しくは近隣の寺院、仏壇・仏具店にお問い合わせください。
戒名がなくても位牌は作れるの?
戒名とは、仏教徒の証です。信仰心の厚い人や先祖代々戒名を作っている、お寺と深く関わりがあるという場合は、生前に戒名を授かっていたり、家族もそのつもりで準備をします。
無宗教であったり、お寺とのつながりがなく、お葬式後の法要を特に行わない方や、故人への思い入れが深く親しみのある名前で作りたい、名前のほうが身近に感じられる、戒名だと呼びかけが難しいなど、多種多様の価値観があります。
位牌の選び方
位牌のサイズは、安置する仏壇の大きさとのバランスも考えて選びましょう。
位牌の種類
一方、通常用いられているのは、順修牌(じゅんしゅうはい)と呼ばれる位牌です。四十九日までは白木の位牌で、四十九日の法要で本位牌へ入れ替わります。
また、本位牌は材質や作り方、デザインなどによって塗り位牌(ぬりいはい)、唐木位牌(からきいはい)、天然木位牌(てんねんもくいはい)、モダン位牌などがあります。
塗り位牌:
漆(うるし)で塗られた黒塗りの位牌のこと。合成の漆を使用したリーズナブルな位牌と、本漆で仕上げた位牌があります。一部、または全体に金箔を施したものもありま
す。
唐木位牌:
黒檀や紫檀などの、唐木素材で作られた位牌のこと。丈夫で重く、耐久性に優れ
ています。
天然木位牌:
天然木で作られた位牌のこと。「さくら」や「ひのき」など。優しい風合いでインテリアにも合い、ライフスタイルに合わせやすくなっています。
モダン位牌:
デザイン性の高い位牌のこと。蒔絵が施されたり、寄木細工を一部に使用したものなど。クリスタルやガラスの素材で作られた位牌もあります。
位牌のサイズ、選ぶ基準
1寸は、約3.03cmです。位牌の「寸」は札の高さを指すので、位牌の総丈と間違えないようにしましょう。
一般的には、4寸~4.5寸がよく選ばれているようです。例えば大型の仏壇のときには、5寸以上というように、位牌の大きさは安置する仏壇の大きさによってもその見栄えは大きく異なります。位牌を安置する仏壇に合わせて、バランスを考えて選ぶとよいでしょう。
すでに位牌がある場合は、先祖の位牌より大きくならないように、もしくは同じくらいの大きさにするのが一般的です。しかし、故人が偉大な功績を残した場合など、先祖の位牌より大きく作ることもできます。
このように、家庭事情に合わせて仏壇とのバランスを考えて選ばれるといいでしょう。
本位牌の注文時に注意すること
位牌の種類、文字の量によっても配列は異なります。
位牌に入れる文字の種類
現代風書体、標準書体、旧字体、変体文字があります。英字も入れられるところもありますが、それぞれの書体を選ぶときはお寺と相談して決めるとよいでしょう。
また、位牌に文字を入れる方法として、彫刻と手書きがあります。彫刻の場合にも、彫り後には金を入れる金文字が一般的ですが、素彫りのまま使用することもあります。
位牌の文字配列の確認
文字の配列は宗派によって異なり、戒名に加えて院号*、道号**、位号***などが上下につく
場合と、平等という考えからつかない場合があります。
また、一人用(個人)、連名(夫婦二人)、俗名(戒名なし)などによっても、文字の配列は異なります。
基本的には位牌を購入した仏壇店にお任せできますが、仕上がりの確認は必要です。
*院号:生前にお寺を建立するほどの多額のお布施をした人、地位や身分の高い人、社会に大きく貢献した人に与えられるものです。
**道号:二文字の戒名の上につけられるもので、字(あざな)にあたるものです。出家者に対する呼び名でもあります。
***位号:仏教徒としての位を表す尊称で、年齢や性別、信仰の深さなどでつけられる号は決まっています。男性には信士、居士などで女性には信女、大姉などがあります。
著名人の戒名
西郷隆盛 南州寺殿威徳隆盛大居士
福沢諭吉 大観院独立自尊居士
樋口一葉 知相院釈妙葉信女
位牌を作ったあとは魂入れ(開眼供養)をします
位牌を捨てる場合には、魂を抜いてものに戻す供養を行います。
魂入れをして位牌ははじめて供養の対象に
古い位牌の処分方法は?
お仏壇の継承者がいなくなったり、管理が難しくなったり、経年劣化で新しく買い替える場合、あるいは先祖の位牌をまとめてひとつにする場合など、古い位牌を処分する(供養する)ときには、「魂を抜いてお焚き上げ処分する」か「永代供養に出す」という方法があります。位牌の形を残すか残さないかの選択です。
「魂を抜いてお焚き上げ処分する」とは、位牌に宿る魂を浄土へ返してあげるという意味があり、処分前に魂を抜くことで、位牌をただの名前の書かれた木札に戻します。その後、お焚き上げで焼却処分します。形を残さないやり方です。
「永代供養に出す」とは、寺院や霊園などに位牌を預けて代わりに供養を行ってもらえる、継続的な供養のシステムです。形を残すやり方です。
しかし、永久に期限もなく供養してもらえるわけではありません。寺院や霊園などによって年数は決まっています。お焚き上げするより費用がかかるのが一般的です。
また、相談できるお寺がない。または、菩提寺が遠方だったり、仕事などで日程の調整がつかないといった場合には、お焚き上げを専門にするサービスを利用する方法もあります。
*お焚き上げ:神社などで古い神札やお守りなどを焼くこと。あるいは、火に御札をかざすなどして吉凶を占うこと。
葬儀で用いた白木の位牌も、本位牌に魂を入れ替えた後にはお寺に納めて「お焚き上げ」をお願いします。
ることは?”]
一方、先祖代々の位牌など複数ある場合にはひとつにまとめることも可能です。
先祖代々の位牌がたくさんある場合は、まとめることもできます。
位牌をたくさん作る地域もある
ところが群馬県には、故人の子供の数と同じ数位牌を作って、それぞれの家庭で仏壇に安置するという習わしがあります。
例えば、故人に3人の子供がいる場合には、人数分、すなわち位牌を3つ作ることになります。
位牌をひとつに纏める(まとめる)ことはできるの?
*三十三回忌・五十回忌:一般的に年忌法要のひとつの区切りとして弔い上げ(最後の法要)が行われます。
**繰り出し位牌:箱型の位牌で、札板をまとめて10枚ほど収納できるようになっています。
***過去帳:故人の名前、戒名(法名)、没年月日、年齢など書かれています。亡くなった順に書かれ後世にも残していけるので、家系図の意味合いが強いです。浄土真宗では、位牌の代わりに使われるものです。
位牌を購入する仏壇店の選び方
一番大切なことは、遺族の気持ちに寄り添い、親身に相談に乗ってくれる仏壇店でしょう。
お店の考え方や店員の接客態度など、お店を訪れた時の印象も仏壇店選びには大切な要素です。また購入後もケアをしっかりとやってくれるお店は信頼ができます。
可能であればいくつかの仏壇店を回ってみて、ご自身にあった仏壇店を探してみることをお勧めします。
なお、「いい仏壇」 では、全国8,000件以上の仏壇店からあ
なたに合った商品を探せます。
まとめ
そしていずれは皆旅立ちのときが来ます。ご自身の悔いが残らないよう、また残されたご家族の気持ちを少しでも和らげることができるよう、終活にあわせて位牌を生前に準備するのもいいかもしれませんね。