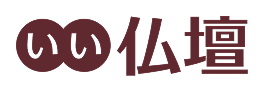新潟の白根仏壇の頑丈さはバツグン!200年経っても新品同様?

300年の歴史をもつ新潟・白根仏壇。高い耐久性と、見た目の優美さを兼ね備えた特徴と成り立ちについて紹介します。
白根仏壇の歴史
白根仏壇の歴史は江戸時代中期に伽藍師(がらんし)という寺院専門の宮大工・長井林右エ門が京形の仏壇を模作し、彫刻を施した白木仏壇の製作がはじまりとされています。
その後、水害に苦しむ白根の人々の信仰の対象として仏壇は各家庭に受け入れられ、18世紀後半(江戸時代天明年間)には独自の技術・技法と分業化の生産体制が確立されました。
信仰心が深い新潟の地でも新潟白根仏壇が主に製造される新潟市、白根市は、現在も県内最大の仏壇生産地として知られています。300年以上にわたり引き継がれてきた同仏壇発展の背景には、以下の理由があったと考えられています。
- 親鸞や日蓮ゆかりの地であることから浄土真宗や日蓮宗が広まり、仏教文化が民衆に浸透していったこと。
- 高温多湿な気候帯が漆の乾燥に最適だったこと。
- 新潟港から東北などへ仏壇を出荷する物流ルートを利用したこと。
白根仏壇の特徴
京都の仏壇を源流に持つ新潟白根仏壇は、豪華で優美な品格と堅牢な造りが特徴です。製造は木地・彫刻・金具・塗箔・蒔絵の5工程に分かれており、各工程を専門の職人が分業して仏壇を作り上げています。
解体・組立が容易な独自の技法は、仏壇の耐久性を損なうことなく補修・修復を行うことができ、100年から200年後も新品同様へ生まれ変わるといわれています。 新潟・白根仏壇の主な伝統的技術・技法は、以下の通りです。
- 木地の材料はヒノキ、寧欅、桜、ヒメコマツ、杉などを使用する。
- 木地の構造は「ほぞ組み」による組み立て式。
- 組立・解体が容易な「平枡型」による「三屋根」の宮殿作り。
- すべて手作業による彫刻と金具加工。
- 塗装・蒔絵は本漆塗り、金箔は永久に変色をすることがない本金・本金粉を使用。
- 各部の構造は「柄組み」による組み立て式。
白根仏壇の産地で仏壇店・仏具店を探す
※白根市は、かつて新潟県下越地方にあった市。 2005年の新潟市への編入合併によって消滅し、現在は新潟市の政令指定都市移行により南区の一部となっています。