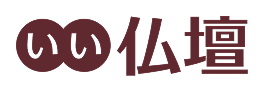位牌の種類・分類


位牌には使われる場所や素材によって種類があるほか、宗派によっても違いがあります。
大切なものではありますが、最近ではあまり身近ではなくなり位牌についてあまりよく知らない、という方も増えてきています。
そこで今回は、位牌の基本的な説明から種類までを紹介します。
位牌とは
親族は位牌を通して亡くなった方を偲び、冥福を祈ります。仏教では死後49日目の法要で、お坊さんが亡くなった方に引導を渡すことで成仏できるとされています。成仏した魂は位牌にとどまるため、一般的に四十九日法要の際に位牌を用意します。
位牌の分類
内位牌(うちいはい)
内位牌の表側には戒名と生前の姓名(俗名)を書きます。裏側には、亡くなった年月日と享年を書きます。この内位牌は四十九日法要まで使用します。
なお、同じく白木の仮位牌でも、お墓にもっていくなど屋外で使用するものを野位牌といいます。
本位牌(ほんいはい)
本位牌の種類
塗り位牌
装飾として金粉や金箔、金色の塗料が使われます。
唐木位牌
天然木位牌
宗派による違い
位牌そのものを用意しない宗派
浄土真宗(真宗)
ただし、最近では手を合わせる対象として位牌を希望する門徒の方もいらっしゃるようです。このような場合は、菩提寺に相談してみることをおすすめします。
位牌の戒名(法名)の書き方が違う宗派
真言宗
浄土宗
禅宗
日蓮宗
位牌や戒名(法名・法号)については、宗派のほか地域の習わしやそれぞれのお寺の考え方によっても異なることがあります。詳しくは菩提寺や地域の仏壇仏具店に確認しましょう。
位牌はどうやって選ぶ?
位牌は基本的に仏壇の大きさに合わせて選びます。仏壇の大きさを考えずに大きい位牌を選んでしまうと、仏壇に入らないこともあるので購入前に仏壇のサイズを確認しておくとよいでしょう。また、先祖の位牌がある場合は、それよりも背が低い位牌を選ぶのが一般的です。
位牌の大きさは昔から使われている尺貫法で表記されます。1寸=3.03cmで、2寸から8寸まであり、販売店によっては何号(=寸)と表記されることもあります。
寸法は札板と呼ばれる中心の板の長さを指すため、実際の位牌の高さはそれよりも大きくなるので注意が必要です。総高と表記されていれば、それは全長を指しています。
位牌の大きさが決まったら、予算に合わせてデザインや素材を選んでいきます。素材や細工、製造工程の違いによって価格に幅がありますが、1万円~数万円程度の位牌が売れ筋のようです。
海外で製造された安価な位牌もありますが、故人を祀るためのものなので選ぶ基準は値段だけではなく、丁寧に作られた国産の位牌を選びたいという方もいらっしゃいます。
まとめ
しかし、実際は誰かが亡くなってから四十九日までに準備をするため、戒名を彫る時間を考慮すると非常に短い時間の間に選なければならないケースも多々あります。詳しいことを調べる時間もないまま選んでしまうこともあるかもしれません。
故人を祀るためのものですので、専門家の意見を聞いて選ぶことをおすすめします。また、位牌に関してわからないことがある方、お悩みがある方はお気軽にお問い合わせください。