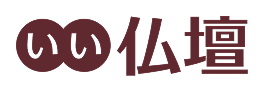樒について

今回は、「樒とはどんな植物なのか」、「仏教と樒のつながり」、「樒と榊の違い」、「樒は葬儀でどのように使用されるのか」など、樒について詳しく紹介します。
樒とはどんな植物なのか
3月から4月にかけて、淡い黄色のひらひらとした細長い花を咲かせます。主に寺や墓地の周りに植栽されています。樒は、花や葉、実、根、茎まで、すべてに毒性があり、特に実は、食べると死亡する可能性があるほど有毒で、植物として唯一、「毒物及び劇物取締法」により、劇物の指定を受けています。
樒という名は、四季を通じて緑が美しいので「しきみ」「しきび」と呼ばれるという説と、実が毒を持っているという意味の「悪しき実」から「悪」をとって「しきみ」と呼ばれるという説があります。また実が扁平な形をしていることから「敷き実(しきみ)」と呼ばれるという説もあるそうです。
樒と仏教のつながり
さらに、弘法大師が密教の修行の際に、青蓮華の代用として樒を使ったという言い伝えがあります。樒に、密の字が使われているのは密教とのつながりを示しているといわれています。
現代では、日蓮正宗のように、仏壇や墓には生花は供えずに樒のみを供えるという教えの宗派もあります。浄土真宗でも、華瓶に水を入れ、生花ではなく樒を挿して、香水として仏壇に供えています。
樒と榊の違い
榊は「境木」とも書き、神域と俗界との結界を示すために神社の周りに植えられています。
樒と榊は、葉の形で見分けることができます。樒の葉は波打ったような形で、榊は平べったい楕円形です。榊は生花店だけでなく、スーパーなどでも購入できますが、樒は生花店でも販売している店は少なく、通販や葬儀社、仏具店などで購入することができます。
樒の香り
ちなみに、樒の「illicium(イリシウム)」という学名は、ラテン語で「魅力で引き付ける、誘い込む」という意味の「illicio」が語源となっています。つまり、香りで引き付けられる木という意味です。
樒は、白檀のような香木がほとんどない日本においては、香木の代用品として使われてきました。
独特の香りと強い毒を持っていることから、邪気を払う力があるとされ、悪霊除けやお清めとして使うほかに、土葬の遺体を動物から守るために、樒を墓の周りに植えていたそうです。現在でも、通夜まで自宅で遺体を安置する際の枕飾りの仏具と一緒に一本花として供えたり、納骨式に樒を供えるのは、その名残りです。
また、ひと昔前までは、遺体の腐乱臭を防ぐために、納棺の際に、ドライアイスの代わりに樒を棺に敷き詰めていました。
葬儀での樒の使われ方
現在では、全国的に祭壇は生花で飾られていまが、京都では祭壇に生花を飾らずに、樒を飾っている地域もあります。
まとめ
実際には、葬儀での樒の使い方や手配の仕方など、ご不明なことが多いと思います。また葬儀に関する些細な事でも構いません。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。