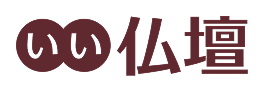錫杖とは

主に修行僧が持つもので、比丘十八物(びくじゅうはちもつ:修行僧が持つべき十八の道具)に数えられるほど、重要な道具です。
錫杖はさまざまな使い方があり、宗教的な意味も多くあります。今回は錫杖について、詳しくご紹介します。
錫杖の形態
遊輪は先端部分に通してあり、自由に動くようになっています。錫杖を動かせば、音を立てて遊輪も動き、輪同士がぶつかり合い、シャンシャンと独特の音を立てるのです。この音色が錫(すず)の音に似ていることから、錫杖という名前が付られたという説もあります。
柄の部分は杖として使うこともあるので、木製で、長さは160㎝から170㎝が一般的です。現在では大人の背丈ほどですが、昔は平均的な身長が今ほど大きくなかったので、だいぶ長い杖だといえます。また、前述のように30㎝ほどの短いものもありますが、これは手錫杖と呼ばれ、儀式用として使われていました。
錫杖の用途
また、武器として使われていたこともあります。僧侶が武器を持つ姿というのは、あまり想像ができないかもしれませんが、日本では平安時代末期から僧兵が組織されはじめます。寺院同士による権力争いや、朝廷に対する武力的な圧力にも僧兵が関与していました。
僧兵が蜂起する場合は刀などを手にしますが、偶発的な戦闘は錫杖を使用したといいます。この武術は杖術となり、後世にも伝えられています。
仏教での錫杖の意義
錫杖の先端は五輪塔をかたどった大きな輪になっています。そこに小さな輪が通されています。小輪の数は、4つ付いているもの、6つのもの、12のものの3種類あります。小輪が4つのものは四諦(したい:仏教が説く基本的な教えで、苦諦・集諦・滅諦・道諦のこと)を表しています。12のものは、十二因縁(苦悩を断つための十二の事柄)を表します。そして、6つのものは、六道(輪廻転生する六つの世界)のことです。
錫杖には浄化する力があるとされ、常に右手に持つとされています。
錫杖の仏教における意義は、「錫杖経」というお経にあるようです。錫杖の音色を聞くと、どの世界に居ても誰でも煩悩から解き放たれたいと思うようになり、悟りを得られる修業に導いてくれるという内容です。
錫杖と地蔵菩薩
錫杖を持っている仏像は、地蔵菩薩です。先にもご紹介したように、錫杖の輪の数には3種類ありますが、そのうち地蔵菩薩が持っているものは、六つの輪がある錫杖です。
地蔵菩薩はそれぞれの世界に行くために姿を変えて救いの手を差し伸べてくれます。その姿を変えた地蔵菩薩を表現しているのが、六地蔵なのです。そして、それを表すために、六輪の錫杖を持っています。
仏具としての錫杖
また加持祈祷(手印や真言を唱えて衆生を救済する)でも錫杖が使用されます。お祓いしたい人や物を錫杖により、因縁を断ち切るというものです。
このように、錫杖にはさまざまな役割があります。葬儀や法事のときにも見かけることがあるかもしれません。そのときは、錫杖の役割を思い出してみてください。
まとめ
一方、宗教的な意味合いも多く持っており、さまざまな儀式で使用されています。葬儀などにも使用されることがあります。
葬儀に関して、疑問やお悩みなどあれば、どのようなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。