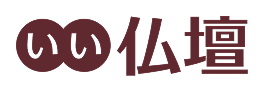浄土真宗大谷派の仏具について
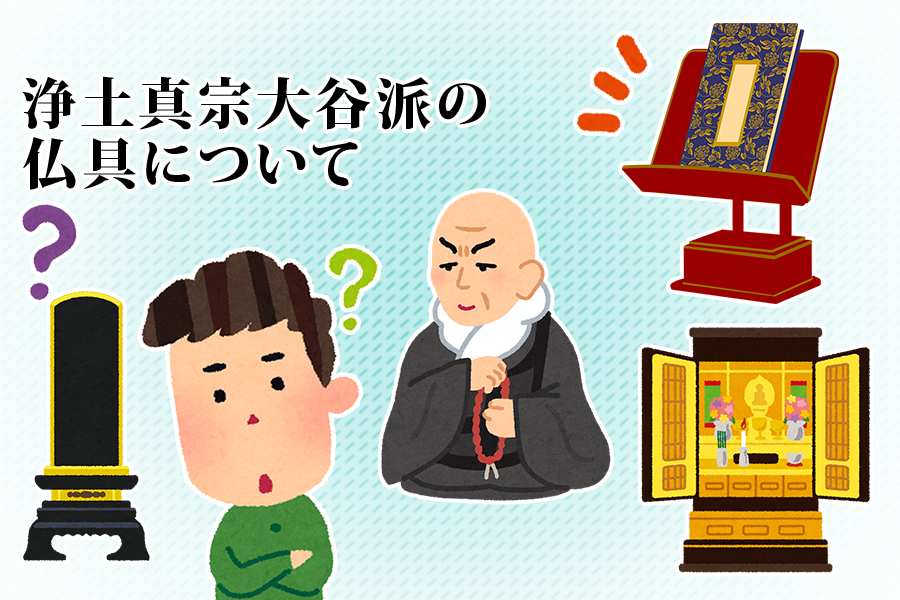
また、真宗大谷派の仏壇には位牌は安置しません。鶴亀燭台を飾ったり、お茶やお水を入れる茶陶器は用いないというように、浄土真宗や真宗大谷派だけ見られる特徴があります。
真宗大谷派の仏壇
また、真宗大谷派の仏壇は金仏壇と決められているわけではなく、唐木仏壇・モダン仏壇を選んでも問題はありません。
浄土真宗の仏具の特徴
浄土真宗では、位牌を置きません。浄土真宗では、仏壇はご本尊(阿弥陀如来)をお祀りするための場所です。阿弥陀如来を信心することで、人は亡くなるとすぐに仏になるとされています。故人の魂は浄土に行くとされているので、故人の魂を祀る位牌を安置する必要がないのです。一方で、故人の名前を記した過去帳を用います。
また、命日・お盆などにお供えする霊供膳(りょうぐぜん)を用意しないとされているため、汁物やお漬物を盛るお椀を使いません。他にも、故人が行く浄土には八功徳水という水があり、8つの功徳を備える水には豊富な量・喉の渇きを潤す効果があるため、お水を供えしないという特徴があります。
真宗大谷派の仏具
真宗大谷派の仏具の並べ方
まず、金灯篭はご本尊と脇侍の間に吊るします。瓔珞・輪灯は脇侍の外側に飾ってください。法名軸を飾る場所は仏壇の左右の壁面内側で、脇侍の外側にお祀りします。上卓には、火舎香炉を真ん中に置き、両側に華瓶と仏器を一対ずつ並べ、供笥は上卓の両脇に置きます。前卓には、三具足または五具足を配置します。
三具足の場合は、真ん中に土香炉、右に鶴亀燭台、左に花立ての順番で並べます。また、五具足の場合は真ん中に土香炉、両側に鶴亀燭台と花立ての順番で並べます。花立てには季節ごとの生花を挿すと雰囲気に風情がでます。仏壇の最下段には、真ん中に和讃卓と和讃箱を置き、右側に過去帳台・過去帳を配置します。仏壇の手前には、真ん中に経卓を設置し、右におりん、左に御文箱を並べます。経卓の上には、左からマッチ消し・線香立て・経本・香合の順番に置きます。
真宗大谷派の仏像、脇侍
ご本尊の両脇に飾られる脇侍は「帰命尽十方無碍光如来」と「南無不可思議光如来」の掛け軸を用意しましょう。お祀りするときは向かって右側に「帰命尽十方無碍光如来」、左側に「南無不可思議光如来」の掛け軸を安置します。ただし、住んでいる場所や菩提寺によってお祀りする方法が違う場合があります。はじめてご本尊や脇侍をそろえる方は、お寺や仏壇・仏具店に相談をすると間違いがありません。
まとめ
仏壇・仏具の購入を検討されている方で、信仰している宗派の仏壇や仏具の決まりごとについて不安な方は、ぜひ一度ご相談ください。