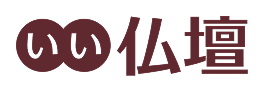払子とは

この記事では、払子について、また、払子を扱うお坊さんについてお伝えします。
払子とは
お坊さんが胸元に提げていたり、手に持ったりしているのを見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。動物の毛や麻を原材料にして、束ねて柄をつけたもので、埃を取るハタキのような見た目をしています。
払子の役割は?
インドのジャイナ教では、今でも払子が元々持っていた用途で使われているようです。しかし、現在の日本においては、お坊さんが威儀を正すために、やや形式的な目的で使用されています。
払子に高価な材料は用いない?
払子の用途
禅宗では法要の導師をつとめる時や高僧が説法する際、また法要の導師をつとめる時に手にします。前後左右、上下に振り動かして使用します。払子は合掌の人差し指と親指の間から柄の末を出し、角度が45度位になるのが適切な持ち方だとされています。
浄土宗では、内陣法要では入堂直後と退堂直前の2回、外陣法要では仏前と祭壇の計4回振ることになっており、それ以上みだりに振ってはならないとされています。故人の煩悩や穢れ、迷いを払うことで、故人が悟りの心を開くことを認め、お釈迦様の弟子になるという意味合いが込められています。払子はその作法とともに、代々受け継がれていくものです。
払子の入手方法
ちなみに、払子の毛の滑りをよくしたり、静電気を防いだりするための「払子用リンス」というものもあります。葬儀は故人がお釈迦様の弟子となって旅立つ厳粛な儀式ですので、参列者がしっかりお別れの時間を取り、お見送りできるよう、お坊さんはきちんと払子の手入れもしています。
お坊さんのことを導師と呼ぶのはなぜ?
元々導師という呼び名は、仏教の教えを説く、説教者の役割を持つ人を表すものでした。しかし、最近ではお葬式や法要の中心となって式を執り行うお坊さんの指す言葉になっています。
導師としてお葬式などを行うことができるのは、住職などの役職に就いている高僧だけです。
まとめ
今後、もし身近にご不幸があってお坊さんが払子を使っているのをご覧になったら、ぜひ、高僧が故人の穢れや迷いを払い、導いている、ということを思い出して頂けたらと思います。
故人をしっかりと見送りたい、と思っても、突然のお別れで何をすれば良いのかが分からない、葬儀をどこにお願いすれば良いか分からない、という方もいらっしゃることでしょう。
個人でご対応なさるには限界もあります。ご相談やお見積もりなど、お気軽にお問い合わせください。安心してご依頼いただける当社のおすすめの業者様をご紹介いたします。